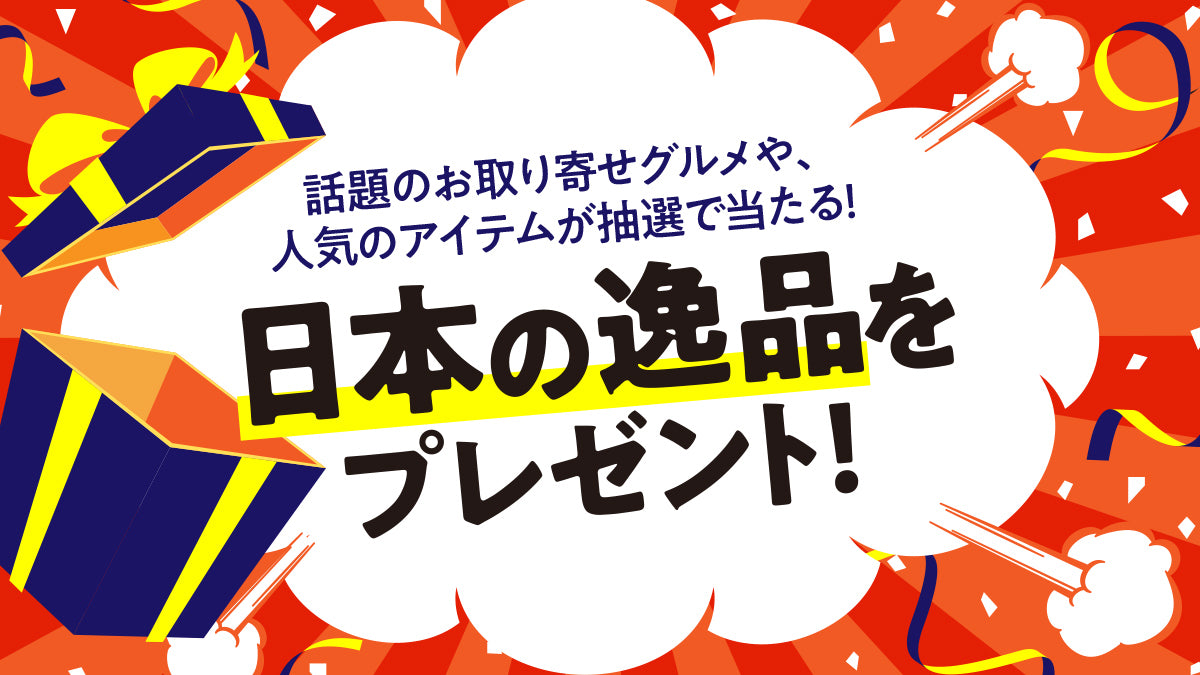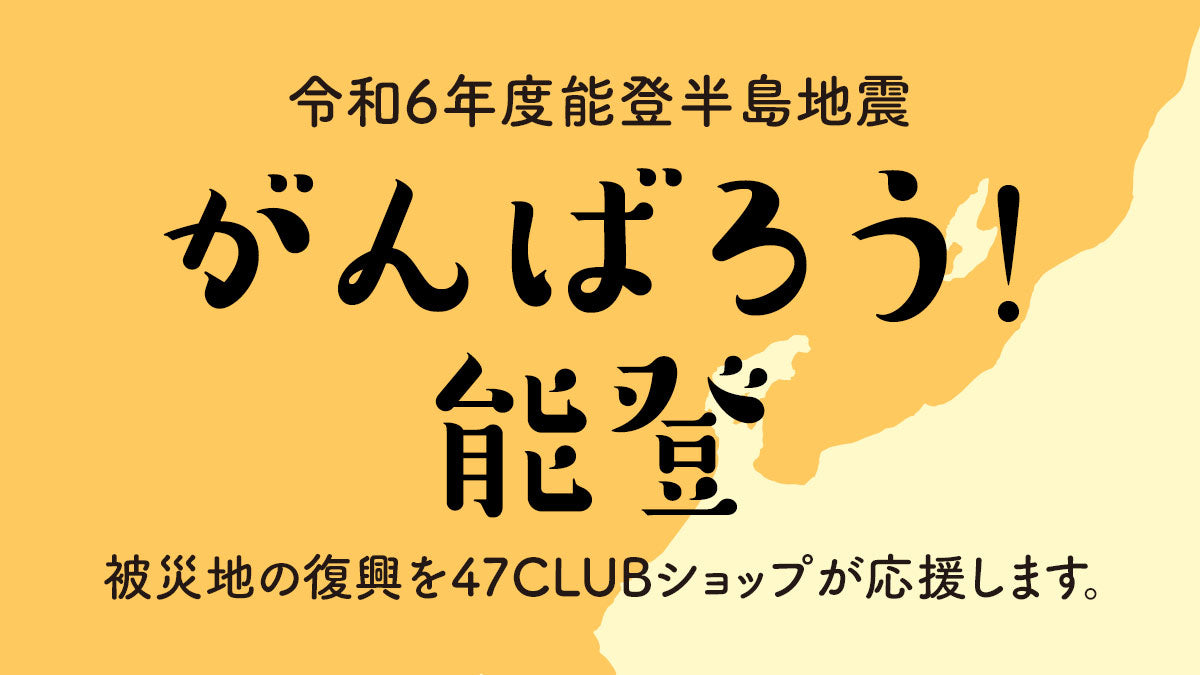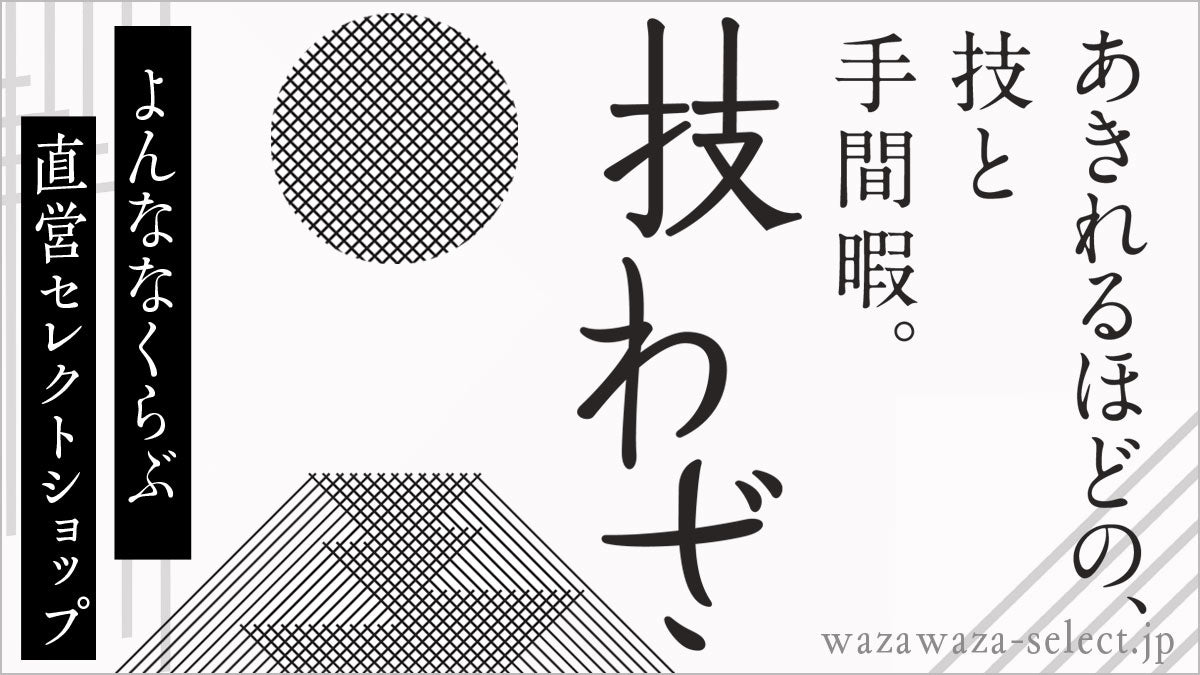ぬか漬け
ぬか漬け専門店菜香や(なかや)
茨城県筑西市下中山595-4*
フード・アクション・ニッポン アワード2020
フード・アクション・ニッポン アワード2020
ミルキークイーン米品種「有機米熟成ぬか床」が100産品に選定されました。

菜香やでは日々、様々なぬか漬けを作り研究を重ねてきました。

ぬか漬けってなあに?
発酵食品が話題の今、免疫力を高める乳酸菌をたっぷり含んだ「ぬか漬け」が注目されています。
一般的にぬか漬けは「植物性乳酸菌による発酵食品」と言われていますが、実はそれだけではありません。
乳酸菌以外にも酵母菌や酪酸菌、また各種細菌類などの様々な微生物が混じり合い、発酵された味によってできています。
そもそも乳酸菌は米ぬかには存在せず、野菜の切れ端などに存在する乳酸菌をぬかをベッドの役目として乳酸菌を育てるのがぬか床の目的です。
そのため、”捨て漬け”という作業を繰り返して乳酸菌を増やし、水分・塩を足してメンテナンスをしながらようやくぬか床が出来上ります。
ぬか漬けは非常に奥深い発酵食品です。そのため、ハードルが高く敬遠する方もいらっしゃるかと思います。
それでも昔から日本の伝統食として伝わってきたのには美味しいだけではなく、栄養面でも優れているすばらしい食品として見直されているからではないでしょうか。
手作りのぬか漬けは「美味しい」「体に優しい」「楽しく作れる」生活を豊かにしてくれる優れた食品なのです。

美味しいぬか漬けのつくりかた【簡単ぬか漬けレシピ】
基本の漬け方はとっても簡単!
【菜香や流】美味しいぬか漬けの漬け方
①野菜の準備
野菜にひとつまみの塩をよく揉み込んで、30分以上おきます。
*「ひとつまみ」の目安は、親指・人差し指・中指でつまめるくらいの量です。
[効果]
・ぬか床の味が浸透しやすくなり、漬ける時間短縮!
・緑黄色野菜が色良く漬け上がります。
・野菜の余分な水分がぬか床に入らず、お手入れ楽チン。
*塩もみをしなくても大丈夫な材料もあります。
②ぬか床に塩を入れよく混ぜる
ぬか床にもひとつまみの塩を入れてよくかき混ぜ、平らにならします。
ぬか漬けを作り続けていると、徐々にぬか床の塩分が減ってきます。そうなると味がしなくなったり、雑菌・カビが発生しますので、毎回塩を足してください。
③野菜をぬか床に入れる
野菜の水分をキッチンペーパー等でよく拭いてから、野菜どうしが重ならないようにぬか床の奥まで入れます。野菜を入れ終えたら、ぬか床を平にならしてください。
④仕上げをして冷蔵庫へ
キッチンペーパーで容器の縁を綺麗に拭います。また、キッチンペーパーを丸めたものを容器の四隅に入れ、蓋をして冷蔵庫で寝かせたら完成です。
*キッチンペーパーは翌日か、ぬか漬けを取り出す時に取り出してください。
ぬか漬けを作り続けていると、野菜の水分がぬか床にうつり水っぽくなりますが、キッチンペーパーで余分な水分を吸収できます。この方法は野菜を漬けている状態でも並行してできるのでとても便利です。
[ぬか床ってどうやって管理するの?]
菜香やではぬか床の保存方法は冷蔵庫をおすすめしています。冷蔵庫だとお手入れがとっても簡単!気軽に始めることができます。
ポイント
・かき混ぜるお手入れが1週間に1~2回でOK!
・低塩分でぬか床を作れるので塩分が気になる方もOK!
・少しの間、漬けすぎても味が変わらない!
[ぬか漬けの食べごろっていつ?]
野菜は冷蔵庫だと2日間くらいで漬かります。取り出してお好みでぬかを軽く拭い、切ってお召し上がりください。
菜香やではミルキークイーン米のぬかを使用し、それが他にはない甘い味わいを作り出しています。
ぬか漬けはすべて洗い流さずに召し上がっていただくのがおすすめです。
[漬かり具合の目安]
1日 サラダ感覚のぬか漬け
2日~ しっかりとした味のぬか漬け
5日以上 発酵が進み旨味のある古漬け
*塩辛く感じるときは流水で流すか、薄く切ってお召し上がりください。
[日々のお手入れはたったこれだけ!]
1週間に1~2回、ぬか床をかき混ぜましょう
乳酸菌は20度以上の温度帯で活発に活動します。冷蔵庫で保管すれば毎日かき混ぜなくても良好な状態を保てます。
ただ、常温で(特に気温が高い時期に)保管する場合は毎日かき混ぜてください。野菜を漬けていない時も、かき混ぜるお手入れだけは続けてください。
どうしても長期間お手入れができない場合は以下のように保管しましょう。
*再度ぬか漬けを始める時は2~3日は毎日よくかき混ぜてください。
(塩分濃度・水分量により条件が変わります。様子をみて行ってください。)
[1〜2週間ぬか床のお手入れができないときは]
表面に大さじ一杯の塩をふり、混ぜずにラップをかけて空気を遮断し、冷蔵庫で保管してください。
再度ぬか漬けを始める時は2〜3日は毎日よくかき混ぜてください。
[2週間以上ぬか床のお手入れができないときは]
フリーザーバッグに小分けして、冷凍庫で保存してください。
再度ぬか漬けを始める時は2〜3日は毎日よくかき混ぜてください。
[ぬか床の塩分と水分をチェックしましょう!]
ぬか床に野菜を入れると野菜から出る水分がぬか床に移行して、ぬか床の塩分が薄くなって乳酸菌の過剰発酵状態になります。
乳酸菌の過剰発酵は酸味が強いぬか漬けになります。
また、ぬか床が水っぽくなった状態にしておくと、正常な菌活動が行われず乳酸菌以外の雑菌が繁殖してしまいます。
ぬか床の水分量が多いと嫌な匂いを発する雑菌が繁殖します。
簡単にぬか床の水分を正常に保つための方法はYoutubeで公開中!
[美味しく続けられるようになったら、足しぬかをしましょう]
ぬか漬けを作り続けていると、取り出すときに多少のぬか漬けが付着してしまうため、だんだんとぬか床の量が減っていきます。
そんなときは足しぬかをしてあげましょう。
足し糠をする際には100gに対して7~10%の塩をよく混ぜてからぬか床に入れてください。
200gに対して大さじ一杯の塩と覚えておくと便利です。
そのまま入れてしまうと塩分が薄くなり雑菌や乳酸菌の繁殖につながります。

日本の誇るスローフード【ぬか漬け】
「スローフード」とは、「ファストフード」の反義語として、1986年に北イタリアにあるブラという小さな村で生まれた言葉だそうです。
そもそもファストフードとは「手早く調理され、注文してすぐに提供される食事」を意味します。
手軽に安価で食べられ、味もそれなりに美味しいとあり、このようなファストフードは世界的に広がりを見せていますが、食材の生産者や調理者の顔が見えることなく、どこで生産されたどのような食材や添加物が使用されているのかはっきりとは分からない、という問題点があります。
このようなファストフードの広がりに不安を感じたのが、北イタリア・ブラに住む食文化雑誌の編集者のカルロ・ペトリーニ氏とその友人たちでした。
彼らは「地域に根ざした食材を使用した、丁寧に作られた食事」を大切にしてもらいたいという思いから、ファストフードではなく食材を含め、ゆっくりじっくりと作られた「スローフード」という言葉を作り、現スローフード協会の前身である「アルチ・ゴーラ」という会を発足しました。
つまりスローフードの「スロー」とは、「ゆっくりと食事する」という意味ではなく、「土地土地にあった生産方法で丁寧に生産された食材を食べることで、食生活とその土地の魅力や文化を見直しましょう」ということです。
ぬか漬けはまさしく日本が誇る「スローフード」。
ビタミンB1が豊富なうえ、乳酸菌の整腸作用も抜群です。ぬか漬けに欠かせない「ぬか床」は、米ぬかと塩、水分を混ぜて乳酸発酵させたもので、昔の家庭には必ずあった日本の伝統食です。
日本が誇る「スローフード」を楽しんでみませんか?

ぬか床に含まれる主な微生物
ぬか床は生きています。ぬか床にはぬか漬けを美味しくしてくれる乳酸菌や健康を守ってくれるたくさんの微生物が共存しています。
代表的な菌として、乳酸菌・酪酸菌・酵母菌がぬか漬けの美味しさを守ってくれています。
乳酸菌(にゅうさんきん)
乳酸菌とは、糠の糖質を消費して乳酸をつくる細菌の総称です。
腸内にすむ細菌のバランスを整えることにより、健康に役立っています。乳酸菌の種類は多種多様で200種類以上の乳酸菌が見つかっています。
ぬか漬けに必要な酸味・旨味・風味を引き出すだけではなく、腸内を酸性側に傾け腸内の腐敗を抑えたり、腸のぜん動運動を助けて便秘を改善する効果があります。
さらに最近の研究によって、免疫機能の向上や、中性脂肪・血中コレステロール値の低下といったはたらきも知られてきました。
そうしたことから、近年、乳酸菌はプロバイオティクス(腸内細菌のバランスを改善することによって健康によい影響を与える微生物)として注目されています。
酪酸菌(らくさんきん)
乳酸菌が作った乳酸を食べて、酪酸を作り出す細菌の総称です。
人間の腸内に住み着く善玉菌で、乳酸菌の成長を助けてくれます。
嫌気性の菌なのでぬか床をかき混ぜないでいるとぬか床の内部で菌が繁殖し、嫌な匂いを放ちます。
エネルギー源となって大腸の正常なはたらきをサポートする酪酸は腸内フローラを健康な状態にキープするのにも役立っていることがわかってきています。
酵母菌(こうぼきん)
等やビタミンB群を食べてアルコールや有機酸を生成する細菌の総称です。
発酵するとぬか漬けの甘みや香りを引き出すだけではなく、雑菌の繁殖も抑えてくれます。
酪酸菌とは違い、好気性でぬか床をかき混ぜないでいるとぬか床の表面で菌が繁殖し、増えすぎるとシンナー臭を放ちます。
菜香やの「ミルキークイーン米ぬか床」の特徴
「精米時期」香りが芳醇で、嫌な匂いがほとんどしない
菜香やのぬか床は、精米したばかりの米ぬかを使用します。
脂質が傷んでいない状態なので、米ぬか特有の嫌な匂いがほとんどありません。
そのため、ぬか床で発酵した乳酸菌の芳醇な香りを楽しむことができます。
「品種」まるで「きな粉」のような甘さのある米ぬか
「ミルキークイーン米」の生米ぬかだけを選定して、ぬか床を作ります。
米ぬかを炒らないで使用するのは、精米したばかりの米ぬかの証拠。
品種を限定することで、他にはない甘みのある米ぬかの風味を生かしています。
実際にぬか漬けに使用すると、ほんのり野菜が甘くなるのは「ミルキークイーン米」ならではの米ぬかのおかげです。
「栽培方法」農場がみえる米ぬかなので、安心・安全
「ミルキークイーン米」を生産する米農家さんにも配慮して、栽培方法にこだわって育った米ぬかを使用します。
オーガニック(無農薬)でお米を栽培する大嶋農場様などから、米ぬかをわけていただきます。
玄米の90%以上の栄養価が含まれている米ぬかは、安心してぬか漬けと一緒にお召し上がりいただけます。
ぬか床には、塩分が含まれていますので過剰摂取にはお気をつけください。
「ミルキークイーン米」との出会い
一軒の農家様からはじまります。
弊社の製造場所である茨城県筑西市は茨城県の県西地域北部に位置する市で、複数の河川が流れ水利にも恵まれていることから古くから水田耕作が盛んで、耕地面積は市域の半分以上を占めています。
そんな豊かな環境だからこそ、昔から大切にお米を育てる大嶋農場さんと出会うことが出来ました。
はじめて「ミルキークイーン米」の米ぬかを食べた時、きな粉と勘違いするほど甘みのある米ぬかで驚いたことを今でもハッキリと覚えています。
菜香やでは、「品種」、「産地」、「栽培方法」、「精米時期」にこだわり、混じりけのない精米したての生ぬか「ミルキークイーン米」だけで作ったぬか床を開発しました。
お米にこだわるのと同じように、ぬか床の米ぬかも適した品種に限定することで、他にはない甘みのある美味しいぬか床が出来上がりました。

生産者のこだわり
ミルキークイーン米とは
1985年、食味が良く粘りの強い米の開発を目的として茨城県に設立されていた農業・食品産業技術総合研究機構農研機構(旧農業研究センター)の稲育種法研究室で研究がはじまり、コシヒカリの突然変異として誕生したのがミルキークイーンです。
ミルキークイーンは、アミロースが少ないので粘りが強いという特性があり、食べるとモチモチした食感が味わえます。
全国で栽培されている美味しいお米の品種コシヒカリの受精卵にMNU(メチルニトロソウレア)という突然変異原処理を行って育成され誕生しました。
米の生産調整が開始され、お米の味が良くないと売れない時代になってきてコシヒカリの子供であるあきたこまちやひとめぼれやヒノヒカリなどコシヒカリ同等の美味しさをもつお米がありますが、それらを超えるものとして誕生したのがミルキークイーンです。
ミルキークイーンはアミロースの量が少ない
お米のデンプンの分子には、アミロースとアミロペクチンがありアミロースの量が多いと硬くて美味しくないお米になります。
アミロースの量が少ないと柔らかくて日本人好みのモチモチした食感の美味しいお米になります。
ちなみにもち米には、アミロースが含まれておらずアミロペクチン100%で出来ています。
それであれだけモチモチになるのです。
低アミロース米とは
近年みなさまに好評が良いお米としてよく低アミロース米という言葉を聞く機会が増えてきていると思いますが、低アミロース米とは、先ほど説明したとおりお米のデンプンの分子のアミロースの含まれている量が15%以下のお米のことを言います。
コシヒカリのアミロース含有量は、約17%ほどだと言われております。
低アミロース米の特徴として冷めても硬くなりにくく粘りが強く炊き上がりの光沢があるというのが特徴です。
- 店舗名
-
ぬか漬け専門店菜香や(なかや)
- 店長
-
遠藤
- 企業名
-
有限会社菜香や
- 代表者名
-
遠藤記生
- 営業時間
-
9:00-17:00
- 定休日
-
日曜日
クレジットカード:商品発送時に課金対象となります。ただし、クレジットカード決裁時の締め日及び引落し日はお客様のご利用されるクレジットカード会社にお問い合わせください。
代金引換:商品受け渡し時
銀行振込:注文後、7日以内
コンビニ決済:注文後、7日以内
Amazon Pay:注文時点で即時に課金対象となります。ただし、Amazon.co.jpにご登録のクレジットカード決裁時の締め日及び引落し日はお客様のご利用されるクレジットカード会社にお問い合わせください。
※予約商品のご注文の際には、注文時点でご請求が発生いたします。商品お届け前のご請求となりますが、予めご了承ください。
クレジットカード決済(JCB・VISA・Master・AMEX・DINERS・Discover)
代金引換
銀行振込
コンビニ決済
Amazon Pay
*商品により支払方法が限定されている場合がございます。予めご了承ください。
北海道 1210円 北海道
北東北 990円 青森県 岩手県 秋田県
南東北 880円 宮城県 山形県 福島県
関東 880円 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
中部 880円 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県
近畿 990円 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国 1100円 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
四国 1100円 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州 1265円 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄 2134円 沖縄県
- 送料
金額は各商品により異なります。詳細は各商品ページをご覧ください。
- 代引手数料
代引決済額 代引手数料(税込) ~9,999円 330円 ~29,999円 440円 ~99,999円 660円 ~300,000円 1,100円 300,001円~ ‐ ※30万円以上を超える決済の場合、代金引換はご利用になれません。
※代金引換をご利用いただけない商品もございます。 - 振込手数料
金額はお客様がご利用の金融機関により異なります。詳細はご利用の金融機関へお問い合わせください。
ご注文後通常1週間以内
ご注文完了後30分間はキャンセルが可能です。キャンセルをご希望の場合、マイアカウントページから、注文履歴>注文詳細へすすんでいただき、[この注文をキャンセル]ボタンをクリックし、キャンセルしてください。
銀行振込、コンビニ払いをご利用のお客様は振込をしなければ自動的にキャンセルとなります。
代引き決済をご利用のお客様は恐れ入りますが注文詳細のお問い合わせフォームよりキャンセルのご希望のお問い合わせをいただけますようお願いいたします。
原則として、キャンセル可能時間(ご注文後30分間)経過後のキャンセルおよび返品、払い戻し等はお受けできませんのでご了承ください。
ただし、当サイトで販売した商品において、不良品であった場合、ご注文いただいた商品と異なると当社または各ショップが判断した場合、返品・交換を承ります。
商品の返品・交換については、ご連絡期限内(※)に、ご注文履歴ページに設置されているお問い合わせフォームから、当社または各ショップまでお申し出ください。
※ご連絡期限
ご連絡期限は商品により異なります。詳細は各商品ページをご覧ください。商品ページに記載のないものは以下となります。
・商品に賞味期限の記載があるものは賞味期限内(ただし、最長で、商品到着後7日以内)
・商品に賞味期限の記載がないものは商品到着後7日以内
内容を確認したうえで、返品・交換を承るか否かのご連絡を差しあげます。
不良品であった場合、ご連絡期限以内の返品・交換にかかる送料につきましては、当社または各ショップ負担とさせていただきます。
なお、お客様のご都合の場合や、一度ご使用になった商品、お客様の責任でキズや汚れが生じた商品、また、ご連絡期限を経過した場合については、返品・交換はお受けできませんのでご了承ください。
※商品により、あらかじめ商品ページにおいて返品不可またはキャンセルおよび払い戻し不可の条件をあらかじめ明示した商品については、原則として、お申し込み後の返品、キャンセルおよび払い戻し等はお受けできませんのでご了承ください。
必ず各商品ページにある「返品・キャンセルについて」の項目をご確認のうえ、ご注文ください。
キャンセル手数料について
体験型イベント商品や予約商品に関してキャンセルを希望される場合、所定のキャンセル手数料をいただく場合がありますので、ご了承ください。
本ショップおよび本商品の返品・キャンセル条件について
(こちらに記載がない場合には上記のみ参照ください)
お客様都合による返品は原則としてお受けできませんが、万が一不良品があった場合は商品到着後5日以内に弊社にご連絡の上、送料着払いにてご返品後、良品と交換いたします。
【良品とのお取替えにつきまして】
お届きになりました商品に不良がある場合は、異物が目視で確認できる写真か現物をお送りいただき、弊社で不良品の確認が取れましたら直ちに良品と交換させていただきます。
弊社での不良品の確認が取れない場合は誠に申し訳ございませんが、交換等のご対応ができかねますのでご了承ください。
商品の不良が確認された場合、基本的に同製品との交換対応とさせて頂きますが、 商品在庫等の関係により同製品が準備できない場合は返品送料含めて全額の返金をさせて頂きます。
ご連絡に使用するメールアドレスドメイン
xxxx(ダミー)@na-ka-ya.com
携帯電話等でフィルタをご利用の場合はドメイン解除をお願いします。
商品一覧
注目特集
メルマガの登録が完了しました